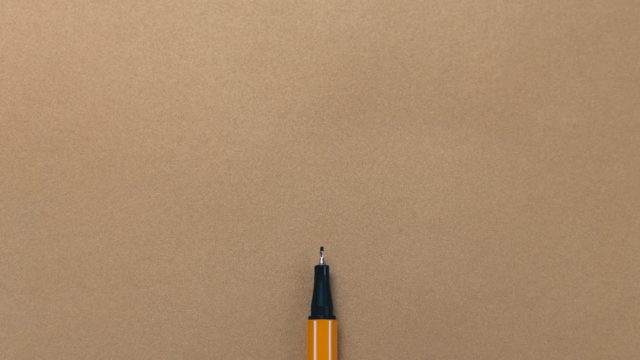今回は2本の対照的な(?)ドキュメンタリー映画を通して、人が動物を食べることについて考えたいと思う。
殺してもいい動物と、殺してはいけない動物
全ての生き物は食物連鎖の連なりに生きている。動物であれば何物もその例外ではない、人間もだ。この「食物連鎖」という考え、「だって食べなきゃ生きていけないんだから」という考えによって、私たちは他の動物を食べることを正当化している。私もその一人だ。
一方で、「中国で犬を食べるのはかわいそう」とか「虫を食べるのは無理」といった言葉を聞くこともある。日本ではバッタを食べる地域があるし、かつては犬を食べていたことも歴史的事実なのだが。

食の文化多様性をどう捉えるかについて物議を醸した映画に「The Cove」がある。これは米アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したアメリカのドキュメンタリー映画で、日本の和歌山県太地町で行われているイルカ追い込み漁を批判的に、その「残酷さ」を強調する形で描いている。欧米ではクジラやイルカ(イルカはクジラの一種)は「知的で感情がある」生き物なので、捕鯨は一般に否定的に捉えられている。映画の中で、隠し撮りによって撮られたイルカ漁の様子は「イルカ漁の残酷さ」を世界にアピールした。イルカが追い詰められ、刺され、血で染まる海。この映画を機に、日本の捕鯨文化に対する国際的な批判が増した。しかし太地町では捕鯨は伝統的な「なりわい」であったし、その点で欧米の人たちが豚や鶏を育て食べてきたこととなんら変わりない。映画「The Cove」やシーシェパード(捕鯨への暴力的妨害活動をも辞さない海外の反捕鯨団体)の「クジラやイルカは知的な動物だから食べるな」という主張には、フランスでブルキニ(イスラム教徒の女性向けの全身を覆う水着)が禁止されたのと同じような居心地の悪さを感じる。なんならペリーが江戸幕府に開国を求めた理由の一つは、当時アメリカで使用されていた鯨油を確保するために太平洋における捕鯨の補給基地がほしかったからじゃないか。土地や文化に根差した食生活を、外側から安易に否定することこそ野蛮というものだろう。

動物たちの「工場」
けれど、「食物連鎖」や「食文化」という言葉ですべてを正当化できるのか、という疑問もある。『いのちの食べかた』というドキュメンタリー映画がある。私が畜産について考えるきっかけになったドイツ・オーストリア合作の作品で、ナレーションはなく、たんたんと穀物や果物、野菜、牛や豚、鶏がどう育てられ加工されるのかをリアルに描く。

ベルトコンベアーで運ばれていく大量のひよこ、ウィンドレス鶏舎の鶏たちが整然と加工されていくさま、人工授精の様子、リズムよく腹を裂かれていく豚、電気ショックで気絶し足を吊られ運ばれる牛……。YouTubeに上がっているこちらの10分ほどの動画では、そのひよこと鶏のシーンが見られる。まさに「工場」だ。ちなみにこの映画の原題は「Our Daily Bread」(私たちの日々の糧)、聖書の言葉である。


自戒を込めて言うのだが、スーパーに並ぶパックされた商品としての肉と、生き物としての鶏・牛・豚との間があまりに隔絶していて、肉を食べるというのがどういうことなのかについて考えるのは難しい。ネット上で「安くてヘルシーな鶏むね肉はダイエットと節約にピッタリ」という文句を読んで、生きた鶏をイメージする人は少ないだろう。動物の肉は栄養豊富だし、それこそ農耕牧畜以前からヒトは肉を食べて生きてきたし、それを否定するつもりは全くない。ただ、現代の人間の欲望を満たすために、動物たちは非常に効率的に機械的に殺されている。人間が「食物連鎖」の上に位置しているから。しかし、この殺し方で正しいのか? 仕事や家事に追われる現代人に、自分が食べる肉は自分で屠殺しろと言うのはもちろん無理だ。でもやはり命を食べる以上、人間は、動物の殺し方にまで踏み込んで考えるべきではないのか、そんなことを考えさせてくれる映画だ。
生きるために命をいただく、というのは自然の摂理である。ハガレンでも、ウサギを殺すことができなかった兄弟が「ごめんな」と言ってウサギの肉を食べ、修行の答えを見つけたシーンは圧巻であった。だけれども、そのように命をいただくとしても、家畜には少しでも快適な環境で育っていてほしい。それがアニマルウェルフェア的な考え方だ。



一方で、そのような理想論を掲げても、既にギリギリのところで頑張っている日本の畜産農家のことを考えると、色々と困難があるというのも想像はつく。畜産農家は輸入飼料に依存せざるを得ずその価格変動の影響を受けやすいし、安い海外産の肉と競争しなければならない。安全性を求めるくせに安さを追求して、少しでも近隣から糞尿のにおいがすればクレームをつける日本の消費者を相手に、アニマルウェルフェアを追求するのは難しいだろう。次回は「そもそも動物を食べない」という考え方について扱ってみたい。